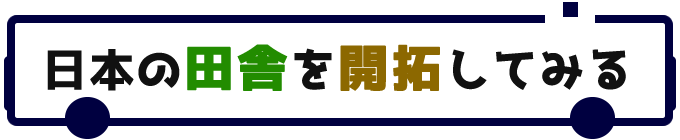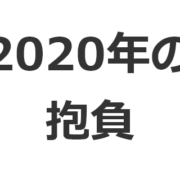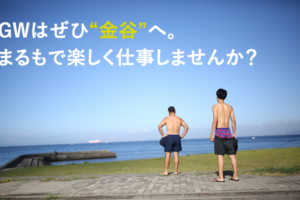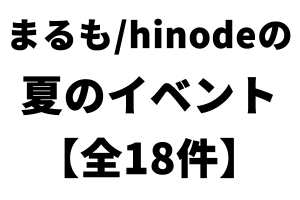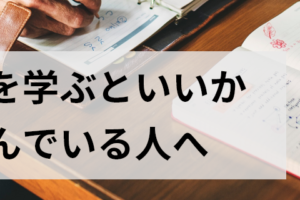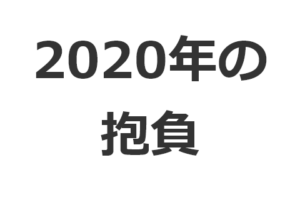台風15号の被災で金谷は停電11日目になりました。
停電からの復旧に山奥でもなんでもない金谷がここまで時間がかかっているのは完全に想定外でした。
ただ被災して現地にいる立場として感じたことを備忘録として残しておきたいと思います。
正直、停電復旧に時間がかかるのはしょうがないというか、専門性が高いことなので何も言えません。
ただ今回の被災から学べること/改善できることとしては「行政の情報管理/広報の形」なのかなと思っています。
そして、行政だけでなく「国民自身の災害に対するリテラシーの向上」ですね。
別に批判ではなく現場の様子であり、これからどうすべきか、という話ですので、ポジティブに話をできたらと思っています!
大量に余る支援物資

これはほんの一部で、もっと多くあります
今回の被災に限らず、大きな災害時にはどこでも起きている問題なんじゃないかと。
金谷がある富津市だけでなく、他の地域でも同様なケースを見受けられたので。
上の写真の通り、支援物資が大量に余っているのです。。
物資が大量にあるなら安心か、というとそうでもないんですよね。
管理に時間と場所がかかる
水がないよりましなのですが、水が無限にあり過ぎます。。。
水って重いので運ぶのも大変だし、電気が復旧してこれらの水をまたどかすとなると大変だろうなと。
もちろん水が必要なときもあったのですが、今はそこまで必要はなく。
支援物資の管理で、時間も場所も余計に使ってしまっているので、「モノでの支援は完全になくしてもいいんじゃないか」と思いました。
はっきり言って、被災後すぐに動いてくれる人たちの支援で物資は足りやすいですし、お金で支援してくれれば行政が一括管理し必要な物資のみを購入し届けることができるので、物資の支援は基本的になしでいいんじゃないかと。
※あくまで基本。災害に特化したNPO団体からは受け付けて個人の支援はなしなど
支援物資の受け入れお断りはどこでもやっていますが、「災害時に物資で支援する」という文化自体を否定し無くしたほうがいいんじゃないかと。。
なんだか寂しさもあるのですが、せめて後述するAmazonほしいモノリストや「SmartSupply」で適切なマッチングをしていくべきだなと思います。
地域経済を圧迫する
金谷では被災があった翌日から地元のスーパーが停電のなか開始しました。
水や食料が不足していたので本当に感謝していますし、大変な時期に営業を再開していて本当に頭が上がりません。
ただ支援物資が届くとなると、わざわざ買いに行かず無料でもらうほうが多くなります。
もちろん物資が足らない状態より良いのですが、支援物資生活が続くとなると地域経済にも影響を与えるなと思いました。
健康への配慮がされていない
なぜかチョコチップクッキーが大量に届いているのですが、被災者が虫歯になるリスクが高まり過ぎじゃないかと。
そしてなぜチョコチップクッキー。。笑
(いや、チョコチップクッキーは美味しいですよね。美味しくいただきました。ありがとうございます!)
もちろん、被災して大変な子供たちを少しでも元気にしたい、という気持ちだと思うのですが、子を持つ親としては普段からお菓子は控えめにし、断水で歯磨きなどがしにくい状態なので、お菓子は控えておきたいのですね。
お菓子に限らず、カップ麺などが大量に届きますが、やはり1週間以上の停電となると健康には悪影響です。
もちろん健康的な食事を物資支給として行うのは難しい部分はありますが、もう少し配慮があると喜ばれるんじゃないか、と思っています。
物資支援は適切なマッチングの仕組みを導入する
千葉市では「Amazonほしいモノリスト」での支援を受け付けていました。
(IT界隈だとごく普通に見かけますが一般的にはそうではないですよね)
他だと「SmartSupply」も同様な仕組みなのですが、市や地域でほしいものをリアルタイムでしっかり発信し、それらを支援してもらう形がいいと思います。
被災直後でいえば「水」「食料」「ガソリン」などあると助かったのですが、今は「乾電池」「ライト」「健康的な食事」「娯楽(ボードゲームやトランプなど)」があると嬉しかったなと思います。
生きるうえで必要なモノは比較的すぐ調達できたので、あると嬉しいモノが後半は嬉しく、たとえばSwitchとか配布があったら子どもは死ぬほど喜んだんじゃないかと(子供じゃなくて大人も嬉しいけど)
支給じゃなくても休憩スペースで遊べる空間があれば親が子どもを遊ばせてゆっくり過ごす/家事をこなすなどできるので、そういった支援もあっていいのかなと思いました。
余る人手と足りない人手

ボランティアなど支援の人手も余る地域と足らない地域が出ています。
正確には余るわけではなく、人材を活かしきれない/適した人材がいない、という表現のほうが正しいですかね。
市全体の状況を行政で管理するのは難しい
まず行政で全てを管理するのって無理だなって思ったんですよね。
この場合の行政は、災害対応に関わりが深い「社会福祉協議会」や「ボランティアセンター」ですね。
市ってかなり広いですし、金谷だと大沢地区という山奥に集落があるのですが、そのエリアが現状どうなっているか、なんて金谷にいる人でさえパッと分かるわけではないので、行政が細部まで自分自身でしっかり把握するのは難しいと思ったのです。
なので、市や行政はプレイヤーとしては全く動かず、ディレクション(指揮)に徹し、各地区との連携に専念してもらうのがよいかな、と思いました。
役割分担と連絡網を整える
ということで、役割分担と連絡網の整備が必須になるかと思います。
連絡網に関しては「電波が繋がりにくい」問題があったので、
- 午前は被災地の現地に滞在&現地責任者とやり取り
- 午後は本部(市役所)に戻り、情報共有や対策を練る
といった具合で動くといいのかなと思いました。
金谷の現地情報が本部に正しく届いている感じがせず。
役割分担は上記の通りですが、区長など現地の責任者が中心となって、
- 現地情報の把握/報告
- 各世帯に訪問/ニーズの把握(しっかり1軒ずつ訪問)
- 必要なボランティアの人数/活動内容の提案
- 支援物資の配達サポート
までしてもらうのがよいかと思います。
行政は、
- ボランティアの募集/受け入れ窓口の設置
- 必要物資の調達/配達
- 現場責任者のフォロー/手伝い
- 公共施設の開放/設備を整える
- 他地域と連携し避難先の確保
でしょうか。
行政のほうが楽な気はしますが、権限を持っている人が動かないと本当にストップするので、市民に権限移譲したほうがいいと思うのです。
あとは行政だからこそできるインパクトが大きいことをするといいと思います。
・神奈川のホテルを借りて避難先を確保する
・発電車を誘致し最低限の電力供給をする
・近隣施設に無料開放/割引開放の要望を出す
などできると良いなと思いました!
行政ができる情報管理/広報とは?
記事のタイトルにも書いた通り、一番すべきことで、今後すべきことは以下の内容かなと思いました。
SNSアカウントの運用
今回の災害でも情報をいち早く仕入れるのに活用したのは「twitter」でした。
- 東京電力のアカウント
- 地域名でのハッシュタグ(#富津市など)
を活用することで、停電復旧の目途や現地情報を仕入れていました。
本当に重要なアナウンスは地域の音声放送で流すべきですが、小さな情報はSNSで流すのがよいなと。
※音声放送って聞き取りにくいし、後で確認したくてもできないから結構不便でした
災害時に活躍するだけでも十分な価値があるので、災害時のためにもSNSアカウントの開設/運用できるレベルにしておくことは大事だと実感しました。
災害用サイトの用意

上記サイトはNHKが用意している「千葉県災害関連サイト」です。
SNSだと情報が流れてしまいますし、情報をストックする場所として適切ではないです。
別にWordPressでサイトなんて簡単に作れますし、この機会に災害時用のWordPressテーマを用意しておけば、災害時にスムーズに適切なサイトが作れていいんじゃないかと。
そういえば、富津市の市役所のサイトでも情報更新していたようですが、市のサイトを見るという発想がなぜかなかったです。
普段からあまり見ないのか、情報更新性が低いと認識していたのか、ソーシャルメディアからの導線がなかったからなのか、自分は全然見なかったんですよね。
そう思うとやっぱりソーシャルメディアの運用って大事なのかなと思いました。
紙文化を減らす
富津市役所に行ってボランティア登録をしないといけないのって手間で。被災地に入る前であれば停電で電波がないわけでもないので、オンラインで事前に手続きしてもらうなど、もっとスムーズにできるなと。
自分自身、ボランティア用紙の受け取り/説明だけで20分程度の時間をお互いに使ってしまい勿体なかったので。
まずはWEBリテラシーを上げることから
正直WEBというよりビジネスリテラシーな気はするのですが、普段の業務としてSNSなんて使わないでしょうし、これらはできなくて当たり前ではあると思うんです。
ただSNSの運用は、大袈裟に言えば「英語で話す」と同じくらい大事なスキルだと思いますし、最低限の知識として身に付けておくべきなのかなと。
災害とは関係ない点で言えば、情報流出や炎上といったトラブルも起きる世の中ですので。
行政のレベルが上がれば市民のレベルも上がりますし、もっと成長していきたいですね。
とりあえず停電復旧してくれないかな・・
ということで、金谷はまだ停電中なのですが、電気が使えないと掃除や片付けにも入りにくく生活を元に戻すこともできず。
リアルタイムな情報はtwitterで発信していこうと思いますので、被災状況や現地情報が気になるかたは以下よりご確認ください。